公益財団法人 日産厚生会 玉川病院
(東京都 世田谷区)
和田 義明 病院長
最終更新日:2025/09/29
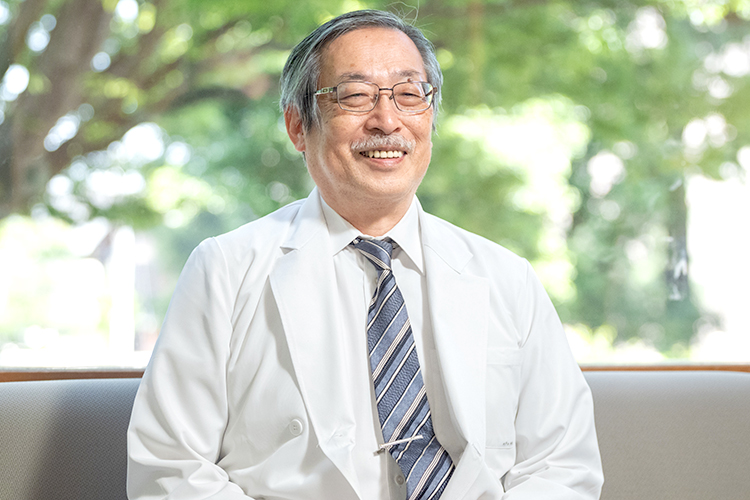
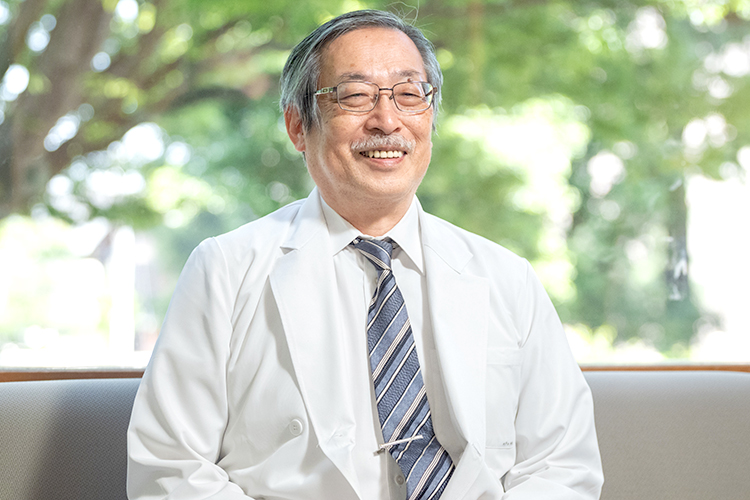
患者にとって最適な医療の提供をめざす
1953年の開設以来、高台にある閑静な住宅地から二子玉川の街を見守り、地域の人々の健康を支えてきた「玉川病院」。公益財団法人日産厚生会の医療機関の一つとして、社会に多大なる貢献を行う公的使命を担う同院。「医の実践と研究」という理念のもと、疾病の予防・治癒につなげるための研究を進めるとともに、地域密着の病院として必要とされる医療の提供に尽力。東京都指定二次救急医療機関として救急患者を積極的に受け入れるとと同時に、がん診療や気胸、鼠径ヘルニア、股関節疾患などには高度で専門的な治療を展開。さらには回復期リハビリテーションにも対応するなど、地域に必要な医療をワンストップで提供することをめざしている。紹介受診重点医療機関となり、地域医療連携にもさらに力を入れるなど、時代の変遷と地域のニーズに合わせて進化を続ける同院について、和田義明病院長に聞いた。(取材日2025年5月20日)
力を入れていることは何ですか?

まず、救急医療です。当院は、東京都指定の二次救急医療機関として、救急患者さんを積極的に受け入れています。医師の働き方改革の影響で、救急体制の維持が困難になっている医療機関もあるようですが、当院では24時間365日体制を維持し、救急科を中心に、病状に応じて各診療科が連携しながら、幅広い医療に対応できる体制を整えています。また、重点領域については「気胸研究センター」「股関節センター」「前立腺センター」「ヘルニアセンター」を設置し、専門性を追究しています。これらの部門では、各疾患の先進的な治療を提供するとともに研究活動も行い、良質な診療につなげていくことをめざしています。それが、最終的に患者さんの利益につながると考えています。今年4月には、これら部門の多くでセンター長が新しくなりました。フレッシュな体制のもとで、先進的な治療に引き続き取り組んでいきたいと考えています。
各部門での取り組みを、もう少し詳しく教えてください。

気胸とは、肺に穴が開いてしぼんでしまう病気で、特に若年層に多く見られます。ですが、気胸を専門的に治療できる医療機関は全国的にも多くはありません。当院の「気胸研究センター」は、約40年の歴史があり、気胸に対して長年にわたり専門的な治療を行ってきました。そのため、遺伝性や難治性の気胸といった症例では、大学病院から紹介を受けることも珍しくありません。また、原発性自然気胸には、小さな穴を3ヵ所開けて行う胸腔鏡手術が一般的ですが、当院では、最小で13mm程度の傷一つから行う単孔式胸腔鏡下手術も積極的に実施しています。「股関節センター」では、変形性股関節症に対する人工関節置換術に力を入れています。手術では、先進のロボティックアームを導入し、骨を削る深さや人工関節を設置する角度などを、術前の計画どおりに精密に実行できるよう努めています。これにより、より安全に配慮した手術をめざしています。
他の部門についてもお願いします。

いわゆる脱腸と呼ばれる鼠径ヘルニアの治療に特化しているのが「ヘルニアセンター」です。当院では、保険診療での腹腔鏡下手術に加え、自由診療となりますがロボット支援下手術も行っています。手術支援ロボットにより、精細な視野と緻密な操作が可能となることで、侵襲や合併症の低減を図り、より早期の回復をめざしています。「前立腺センター」では、前立腺がんに対して、先進的なロボット支援下手術を積極的に実施し、精密な手術で患者さんの排尿や性の機能を維持しながら、より安全な治療をめざしています。また、前立腺肥大症に対する経尿道的前立腺水蒸気治療にも注力しています。この治療法は、従来のレーザーを用いた方法に比べて体への負担が少ないため、高齢者や抗血栓薬を服用しているなどの患者さんにも適応が可能です。今後も、患者さんにとって負担の少ない、先進的な治療の提供に力を入れてまいります。
地域医療連携についての取り組みはいかがですか?

当院では昨年、「地域包括ケア病棟」の運用を終了し、急性期医療に特化した病院としての役割を明確化しました。その背景には、「院内で完結させるのではなく、地域の医療・介護資源と連携しながら、患者さんを適切な場所へつなげていく」という考えがあります。急性期病院としての機能を果たしていくためには、ある程度回復したものの在宅復帰が難しい患者さんを受け入れてくれる地域の施設との連携が欠かせません。現在、近隣の病院や介護施設との連携強化にも取り組み、特に介護施設とは会合を開催し、講演に加えてワークショップを行うなど、相互理解の促進に努めています。また、当院は「紹介受診重点医療機関」となりました。健康相談や日常的な体調管理はかかりつけ医を受診し、必要に応じて紹介を受けて紹介受診重点医療機関の門をたたくという役割分担のもと、地域で開業の先生方との連携も、より一層深めていきたいと考えています。
最後に今後の展望と読者へのメッセージをお願いします。

日本では人口減少と少子高齢化が進行し、「2040年問題」とも呼ばれるように、これからの10年で社会は大きく変化していくと考えられます。若者の減少と出生数の低下により、少子化の波は病院にも確実に影響を及ぼしています。患者数が減少していく中で、私たちは常に、時代や地域のニーズに合った医療をどのように提供していくかを考え続ける必要があります。現代ではさまざまな病気が治療可能となっており、今後は「増えていく病気」と「減っていく病気」がよりはっきりと分かれてくるでしょう。例えば、高齢化により骨折などの整形外科的疾患は増加傾向にある一方で、急性の心疾患は減少していくといわれています。こうした変化に合わせて、医療体制も適宜見直し、柔軟に対応していく必要があります。時代の流れに取り残されることのないよう、環境整備を進めながら、新しい技術や医療も積極的に取り入れていきたいと考えています。
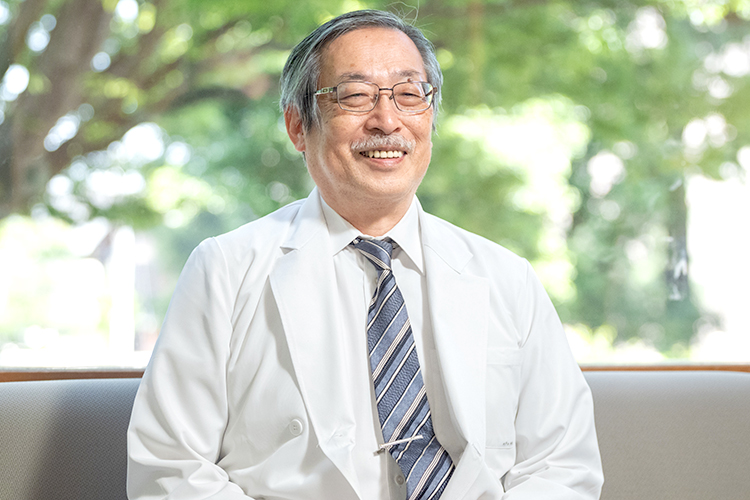
和田 義明 病院長
1981年東京医科歯科大学卒業。同大学医学部附属病院神経内科外来医長、病棟医長、病院掛主任、米国ユタ大学医学部神経内科留学などを経て、1998年より玉川病院リハビリテーション科部長。同院副院長を経て2017年より現職。日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医、日本神経学会神経内科専門医、日本内科学会総合内科専門医。東京科学大学臨床教授。医学博士。日本病院会理事、東京都支部長。
自由診療費用の目安
自由診療とは鼠径ヘルニアのロボット支援下手術/50万円~
※入院期間によっては費用が増額いたします





