昭和医科大学横浜市北部病院
(神奈川県 横浜市都筑区)
坂下 暁子 病院長
最終更新日:2025/10/31


診療科の垣根を越え最善で迅速な治療を追求
2001年に開業した「昭和医科大学横浜市北部病院」は、横浜市北部の地域医療を支える中核病院であると同時に、各国の医師たちが勉強に訪れるほどの先進的な専門医療を提供する大学病院だ。内科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、産婦人科、眼科、リハビリテーション科など豊富な診療科・部門をそろえ、多種多様な患者のニーズに応えるとともに、女性特有の疾患や禁煙治療に特化した外来にも対応している。また市内でも比較的若い都筑区という小児人口が多いエリアにあり、30人以上の小児科医師が地域の医師会と連携しながら小児医療を展開。臨床遺伝・ゲノムを専門とする部門を設け、先天性疾患の小児や乳腺腫瘍などの遺伝に関わる疾患にも、複数科の医師やカウンセラーらが連携するチーム医療であたっている。2024年に病院長に就任した坂下暁子先生は、血液内科を専門に、20年を超える長きにわたり同院に貢献してきたベテランドクター。2024年の病院長就任までは、診療を担当する副院長を7年間務めてきたという坂下病院長に、病院の強みから今後の展望までじっくり聞いた。(取材日2024年11月25日)
まずは病院の特徴を教えてください。

横浜市北部の中核病院として、幅広い診療科と部門を設けて地域医療に貢献しています。救急科では生命に関わる重症患者を積極的に受け入れており、24時間365日体制で対応する循環器部門でのカテーテル治療など豊富な実績があります。分野ごとに内科と外科がフロアを同じくして協働であたるのが特徴で、手術か内科治療かといったディスカッションも行いやすく、それぞれの患者さんにとってベストな治療をスピーディーに提案できるチーム体制です。また、開院当初から当時としてはまだ珍しかったオール電子カルテ方式をとっており、すべての情報を共有しながら診療する環境が整っています。私自身が毎年入ってくる新人の医師、薬剤師とランチミーティングなどでマンツーマンの対話の機会を持つこともあり、風通し良く話しやすい環境が魅力の病院であると感じています。
小児医療にも注力されているとか。

都筑区は横浜市内でも新しくできた区で、居住者の年齢も比較的若い区です。近年は急速に高齢化が進行しつつありますが、それでも周産期・小児医療のニーズは高いエリアです。そこで、小児内科、小児外科、12床のNICUを内包する子ども部門に30人以上の医師が在籍し、総合診療にあたっています。24時間365日体制での小児救急に加え、母体搬送も積極的に受け入れています。出産に特化した病棟を設け、医師や看護師のほか、助産師や薬剤師らのチームが妊産婦の不安を傾聴し、適切に指導する役割を担います。昭和医科大学には保健医療学部や薬学部があり、助産師や薬剤師といったメディカルスタッフが豊富に在勤しているのも特徴です。妊娠中や産後の内服の不安への対応や産後の母子ケアなど、幅広くサポートしています。また先天性異常のあるお子さんに対し、近年新設された臨床遺伝・ゲノム医療センターでは小児科の医師が継続的な診療をしています。
臨床遺伝・ゲノム医療センターについて詳しく教えてください。

がんゲノム医療連携病院として、がんのゲノム解析をしたり、出生前検査、先天性異常など、もともとは腫瘍内科や産科、小児科などでそれぞれ対応していたものを集約。遺伝を専門とする医師やカウンセラーが在籍しています。ゲノム医療は進化を続けており、従来考えつかなかったような治療法が見つかることもあります。近年、出生前検査など比較的簡単にできるようになりましたが、結果だけを提供するようなことがあっては問題です。検査の必要性や結果を受けての対応も含め、正確で現実的な情報を提供する必要があるのです。センターでは、従来臓器別に対応してきた遺伝子異常を一元的に調べるほか、毎週のカンファレンスでチームにより対応を協議。専門性に基づくカウンセリングで患者さんの理解を促します。先天性異常を持つお子さんでも長く生きられるケースが増え、小児の範囲を超えた診療をどうするかという課題にも応えています。
患者のスムーズな受け入れと早期退院に取り組んでいるとか。

予定入院では、総合サポートセンターが事前に患者さんとその周辺の情報をヒアリングします。術後の支援体制や生活環境に加え、薬剤師が内服薬も確認。退院が難しくなりそうな場合は担当看護師が入って調整します。また、長期入院では認知や機能の低下が起きがちです。当院では一般病棟では10日を切る短い在院日数を実現し、ADL(日常生活動作)の低下を防ぐため早期からリハビリテーションを開始します。また、入院に頼らずとも地域で安心して療養できるよう、ドクターtoドクター制度を早くから地域に浸透させました。かかりつけ医と当院の各診療科医師と、2人が主治医となるイメージです。基本はかかりつけ医が診療し、緊急時にはホットラインを経由して各科医師に直接つなぎます。原則お断りしない方針ですが、断るケースが生じた場合には「なぜ?」を厳しく追求します。互いの信頼に基づく体制を維持するために、必要な厳しさだと考えています。
今後の展望と読者へのメッセージをお願いします。
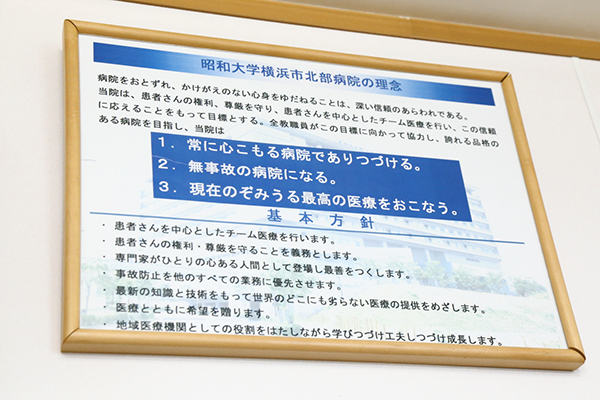
まずは地域の中核病院としての役割を確実に果たすべきですが、加えて高齢化を見据えた対応も必要です。市の要請により精神科救急と病棟、高齢者向けの精神科病棟を設置し合併症を持つ認知症患者さんも受け入れています。また緩和専門の医師や精神科の医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、ケースワーカーらで構成される緩和ケアチームが心と体の“つらさ”をサポートしています。一人ひとりの患者さんがより安楽に治療ができるよう今後も注力していきます。また、災害に強い立地にある耐震構造の病院として、当院は災害拠点病院の指定を受けています。万が一津波により低地の医療機関がまひした場合には、中心的な役割を果たさなければなりません。2024年1月に起きた能登半島地震ではDMATを派遣、普段から訓練も行っています。今後も訓練を通してスタッフのプロフェッショナリズムを育て、地域に安心を提供したいと思います。

坂下 暁子 病院長
茨城県日立市出身。昭和大学医学部を卒業した後、血液内科を専門とする医師として、細胞培養研究などに取り組む。昭和医科大学横浜市北部病院での臨床に加え、昭和医科大学医学部内科学講座での研究・教育や、米国UCLAへの留学も含め幅広い経験を重ね、2017年に昭和医科大学横浜市北部病院の診療を統括する副院長に就任。2024年4月からは同病院長を務める。





