西尾市民病院
(愛知県 西尾市)
田中 俊郎 院長
最終更新日:2025/11/04


平時も災害時も市民の健康を守る存在に
「西尾市民病院」は、1948年に西尾町立西尾地方病院として開院し、1966年に現院名へ改称。現在は22の診療科と321の病床を擁する二次救急病院として救急医療や急性期医療、回復期医療に対応する。2025年4月に院長へと就任した田中俊郎先生は、「地域の医療機関と連携し、救急医療体制を堅持していきたい」と意気込む。社会の高齢化に対応するため、同院は2024年に訪問看護ステーションを開設し、地域包括ケアにも力を注ぐ。患者との距離が近いアットホームな病院として親しまれている同院は、新型コロナウイルス感染症の流行以前から病院祭りなどを通して市民に寄り添う姿勢を貫いてきた。「職種や部署の枠を超え、職員一丸となって市民のための病院づくりを推進していきたい」と語る田中院長に、同院の特徴やめざす姿を聞いた。(取材日2025年7月15日)
まずは、院長としての意気込みをお聞かせ願えますか?

就任初日である4月1日に、職員に向けて所信表明をしました。その中で最も大きなテーマとしてお伝えしたのが、急性期医療を堅持する、ということ。当院は西三河南部西医療圏にありますが、エリアが広大で人口も西尾市だけで約17万人を有しています。その中で三次救急と二次救急を担う病院はごく少数です。その中の1院でも欠けてしまうことは大きな損失となるのです。中でも旧幡豆町にあたる地域や佐久島は他院からの距離もあるため、当院が救急医療をやめてしまっては、地域医療が立ち行かなくなってしまうと思います。そのため、何としても急性期医療を維持していく必要があると考えています。一方で、当院は2つの地域包括ケア病棟も備えています。急性期治療を終えた方が退院し、元の生活に戻るための医療やケアを提供しており、急性期と回復期のどちらにもバランス良く注力していくことが、地域における当院の役割だと考えています。
西尾市民病院の特色について教えてください。

この地域でも珍しいのは昭和大学とつながりのある形成外科です。形成外科の常勤医師がいる病院としての歴史は古く、1976年より同大学から医師が派遣されていました。形成外科には血管腫のあるお子さんをはじめ、あざ、ほくろ、しみ、外傷、やけどの方、また美容に関心のある方などさまざまな患者さんが来られます。同科には多種のレーザー治療器を備えており、予約制で部門化し、力を入れているところです。また眼科も三河地域においては歴史があり、遠方からも患者さんがいらっしゃっています。現在は白内障、緑内障、加齢黄斑変性などの治療を行うほか、斜視と弱視に特化した外来を提供しています。当院のような中規模の病院は、医師の数としては多くはないのですが、それゆえ他科の医師との連携が取りやすい環境です。科を超えて情報を共有する機会が多く、術前術後の連携もスムーズ。医師同士、顔が見える関係性であることは当院の強みだと思います。
放射線治療のために先進の設備を導入されているのですよね?

はい。腫瘍の形や大きさに合わせて放射線を集中的に照射することが可能で、腫瘍の周辺の正常組織への放射線量を少なくすることをめざせます。当院で多いのは、乳がん、肺がん、消化器や泌尿器のがんなど。正常組織への副作用を心配する患者さんにも、積極的に治療を受けていただきたいと考えています。また、2024年度末には、手術支援ロボットを導入し、泌尿器科と外科で活用しています。泌尿器科に関しては、10年以上にわたり常勤の医師が不在で、患者さんにはご不便をおかけしていました。今年4月に常勤の医師が赴任し、さらに手術支援ロボット手術も開始したことで、幅広い治療を提供できる体制が整いました。加えて、新しいMRIも導入しました。MRIは機器の特性上、検査中の閉塞感を苦手とされる方が少なくありません。新機種はシアターを内蔵しているため、映像を見ながら検査を受けていただくことができます。
災害拠点病院としての役割もありますね。

災害拠点病院はDMAT(災害派遣医療チーム)の設置が義務化されており、当院では医師を含む職員による2チームで構成しています。2024年に発生した能登半島地震の際には、このうち1チームが現地入りし、医療支援活動に従事しました。西尾市は能登半島と同様、海沿いに位置している地方都市です。大地震が発生した際には水害のリスクが高い地域であるにもかかわらず、災害対策はあまり進んでいませんでした。災害はいつ起こるかわからないため、DMATに限らず、できる限り多くの職員が発災時に対応できるよう備えておくことが重要です。当院では実践的な災害医療訓練を定期的に実施しています。具体的には災害発生後、多数の傷害者が来院した場合を想定したトリアージ訓練や余震が続く中での診療体制のシミュレーションなどです。他にも模擬患者を病院外へ運び出す、パニックになった人に対応するなど、さまざまなケースを想定し、訓練をしています。
最後に、今後の展望をお聞かせください。
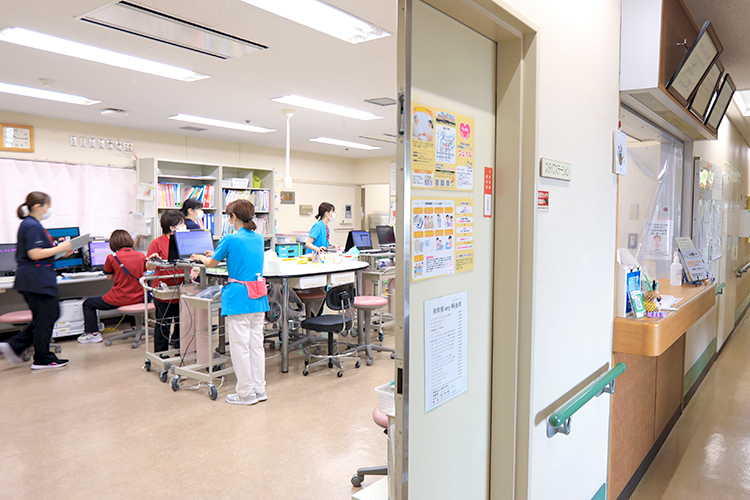
医師の数が少なくアットホームな雰囲気であることは、先ほど申し上げたとおり利点である一方で、医師確保は長年の課題でもあります。これまでも解消に向けて努力を重ねてきましたが、継続して取り組んでいかなければいけないと考えています。ただ、医師の育成や人員確保のためには時間が必要で、今すぐ大幅な増員をするのは難しいのが現状です。今いる職員が部署や職種という枠を超え、一体となって連携できる組織をめざしていくこともまた、患者さんへより良い医療を届けるためには大切なことだと考えています。昨年度には病院フェスタを開催し、手術室の見学や、お子さんの白衣体験といったイベントを行いました。新型コロナウイルス感染症流行前に開催していた病院祭りと比べれば規模は小さなものでしたが、地域の方にたくさん足を運んでいただけました。地域に密着した病院として、スタッフ一丸となって盛り上げていけたらと考えています。

田中 俊郎 院長
1990年名古屋大学医学部卒業。名古屋掖済会病院、津島市民病院、中日病院などに勤務し、2003年西尾市民病院に入職。副院長を経て、2025年4月より現職。専門は循環器病学。日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会循環器専門医、医学博士。





