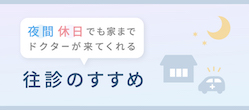医療法人聖仁会 西部総合病院
(埼玉県 さいたま市桜区)
犬飼 敏彦 院長
最終更新日:2023/04/20


多彩な機能で医療と介護、在宅療養をつなぐ
さいたま市や春日部市で病院や在宅ケアセンターなどを展開する聖光会グループの1つとして、1980年にまだ病院が少なかったこの地域に開設された「西部総合病院」。二次救急など急性期に対応する一方で、回復期や慢性期までをサポートするケアミックス型の病院として地域に根づいている。多様な症状に対応するため、急性期治療では脳卒中や骨折、肺炎など高齢者に多い疾患に対応するほか、糖尿病などニーズの高い疾患に特化した外来も開設している。入院では急性期病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟、医療療養病棟と4種類の病棟機能を併せ持ち、入退院時の患者へのサポートや緊急時の受け入れをスムーズにする工夫など、地域の医療機関とともに連携体制を整えることで、医療と介護、在宅医療の橋渡しを実践。「今後、さらにニーズが高まる高齢者医療をはじめ幅広い医療を提供することで地域に貢献していきたい」と語る犬飼敏彦院長に、自身の専門分野であり同院でも力を入れている糖尿病治療や、同院の今後の展望について話を聞いた。(取材日2022年11月9日)
病院の特徴とここ数年の新しい取り組みについて教えてください。

当院は地域に密着したオールラウンダーとして、二次救急などの急性期から、回復期、慢性期までをサポートすることで医療と介護、在宅医療の橋渡し役を担っており、急性期、地域包括ケア、回復期リハビリテーション、医療療養の4つの病棟機能を生かして患者さんを支えています。外来では、各疾患に特化した診療の充実を図り、糖尿病については月〜金曜まで毎日、日本糖尿病学会認定糖尿病専門医が診療を行っているほか、甲状腺や副腎、下垂体などの内分泌疾患を専門的に診る外来も立ち上げました。2022年5月からは外来化学療法を開始し3台のベッドで対応しています。加えて、内科や脳神経外科、泌尿器科での再診を対象としたオンライン診療や、64列CTの導入など、より良い医療を提供するための環境を整備しました。また、地域社会への貢献の一環として、新型コロナウイルスおよびインフルエンザワクチンの接種業務にも積極的に取り組んでいます。
先生は長年、大学病院で診療に携わっていたと聞きました。

今年4月に院長に就任するまでは大学病院に25年勤務していたこともあり、主に先進的な医療に携わってきました。そうしたこれまで培ってきた医療の知識は生かしつつ、ここでは高齢者のニーズに合わせた医療を提供していく必要があります。当院の外来では小児から高齢者まで幅広く診ていますが、特に65歳以上の高齢の患者さんが多くいらっしゃいます。この地域にお住まいのご高齢の方たちが、どこで医療を受けるかは重要な問題です。安心して過ごしていただけるよう、当院の診療を通して地域に貢献していきたいと思っています。退院後に訪問診療や訪問リハビリを実施しているほか、地域で在宅医療に関わる先生方とも緊密な連携をとっています。例えば、急変などで入院治療が必要な場合は当院で受け入れ、症状が落ち着いたらまたクリニックへお戻しするといった体制です。入退院に関しては患者サポート部門にスタッフを配置し、スムーズな調整に努めています。
救急対応で多いのはどのような疾患ですか?

やはり高齢者が多い地域ということもあり、一番多いのは肺炎です。次いで急性胃腸炎などの消化器症状、大腿骨や膝の骨折、脳卒中などです。当院の整形外科は医師が3人常勤し、保存療法だけでなく手術にも対応しているのが特徴です。特に股関節や膝関節の手術に強みがあります。その後のリハビリテーションには、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など専門のスタッフが多く在籍していて、脳卒中や骨折などの急性期治療後の患者さんが、在宅復帰できるようにサポートしています。近隣の高度急性期病院からの紹介で、当院の回復期リハビリテーション病棟に転院して来られる患者さんもいらっしゃいます。地域の開業医院の先生方との連携はもちろんですが、そうした基幹病院との「病病連携」にも力を入れています。また、急性期では糖尿病で血糖が高くなった患者さんへの対応なども多い症例です。
先生は糖尿病治療がご専門だそうですね。

糖尿病はチーム医療が重要だといわれています。そのため当院でも医師、看護師、栄養士をはじめとした多職種チームによるケースカンファレンスを実施し、入院患者さんを対象に一人ひとりに合わせたオーダーメイド治療を提供しています。患者さんそれぞれ必要な治療法や悩まれている内容は違いますので、医療スタッフが問題の解決をめざして「愛の手」を差し伸べていきたいですね。また、糖尿病は長い期間にわたって生活習慣の改善に取り組み、血糖値をコントロールしていかなければいけない疾患です。患者さんご自身がやる気を持って治療に取り組むことが何より大切なのです。時には患者さんを励まし、温かい言葉をかけることで、「また頑張ろう」と思っていただく。私たちがアドバイザーとなって治療をサポートしていきたいと考えています。新しい薬や機器なども積極的に導入しながら、合併症のケアも含めたトータルケアを提供していきます。
最後に、今後の展望をお聞かせください。

現在ある4種類の病棟機能をさらに充実させるために、人員の増加や人材育成に力を注ぐことも必要だと思います。将来の病棟の建て直しも視野に入れながら、今後の病院の在り方を考えていくつもりです。2019年2月には、通りを挟んで病院の向かい側の新棟に健診部門を開設しました。予防や早期診断・早期治療のための取り組みは、ますます重要になってくるでしょう。私の専門でもある糖尿病は「サイレントキラー」とも呼ばれ、初期症状ではわかりにくいため、早く診断するためには定期的な健康診断が欠かせません。今後は講演会などを通じて情報発信をすることで啓発に努めるとともに、糖尿病だけでなく、高血圧や心臓病、脂質異常症など生活習慣に関連した疾患についても生活習慣病という大きなくくりで、病院全体で幅広く取り組んでいきたいです。地域に密着した病院ですので、ちょっとした症状や不安なことなどがあれば、ぜひご相談ください。

犬飼 敏彦 院長
1978年に群馬大学医学部卒業。米国やカナダへの3年間の留学を経て、1994年より獨協医科大学越谷病院(現・獨協医科大学埼玉医療センター)に勤務。一般内科教授、内分泌代謝・血液・神経内科教授、糖尿病内分泌・血液内科教授を歴任し、2019年4月に西部総合病院の院長に就任。埼玉県糖尿病協会会長。日本糖尿病学会糖尿病専門医。日本内分泌学会内分泌代謝科専門医。