医療法人社団聖仁会 横浜甦生病院
(神奈川県 横浜市瀬谷区)
近田 正英 院長
最終更新日:2025/10/07
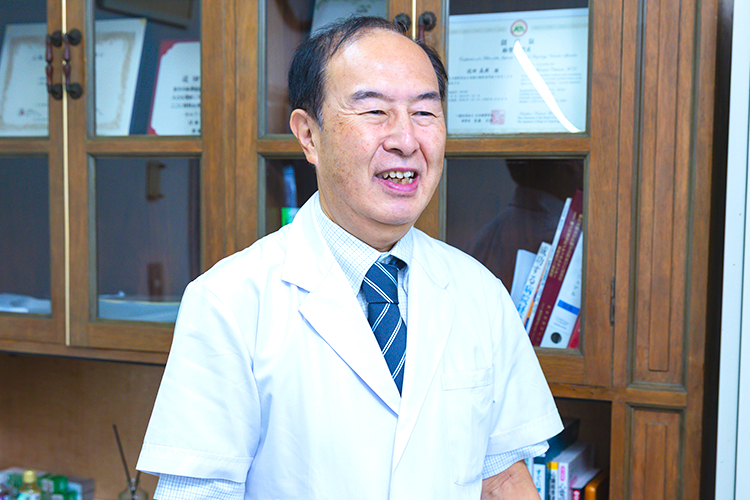
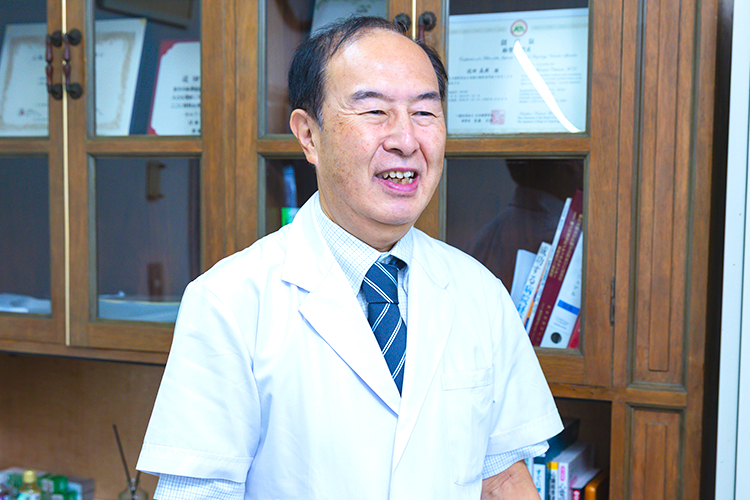
多様な外来、緩和ケアで地域密着の診療を
1968年に診療所として開設され、1995年から医療法人社団 聖仁会に加わった「横浜甦生病院」。瀬谷駅からも近く、幹線道路沿いにある同院では地域密着の医療を続けてきた。一般病棟、療養病棟、緩和ケア病棟を持ち、外来診療や各種の健診から長期療養の入院まで広く対応する同院について、近田正英院長は「緩和ケア病棟を早くから開設し、緩和医療に取り組んできた点も当院の特徴です」と語る。「さらに高齢の患者さんの長期療養に向けた療養病棟もあり、外来診療と併せて地域の医療ニーズに幅広く応えています」。特に外来診療では内科、外科に加え、形成外科、整形外科、耳鼻咽喉科、皮膚科と専門分野の診療までカバー。各種の健診やがん検診で再検査になった人には、同院で消化器内科の医師による胃や大腸の内視鏡検査も受けられる。「今後は診療内容を拡充して地域ニーズへのさらなる対応を図り、長期的には建物の建て替え計画も進行中です」と話す近田院長に、同院と地域医療との深い関わりについて聞いた。(取材日2025年9月11日)
この病院の特徴や診療方針などを伺えますか?

診療所時代を含めると60年近く、この場所で地域に根差した診療を続けてきた病院です。一般病棟39床、療養病棟30床、緩和ケア病棟12床を持ち、特に緩和ケア病棟を早くから備えた点は特徴といえます。さらに在宅医療にも力を入れ、当院からは近隣の高齢者施設を中心に、患者さんの個人宅にも訪問診療に伺っています。内科および精神科の医師が診療を担当し、認知症の周辺症状やせん妄などに対して精神面のケアまで行えるのも強みの一つ。そのほか各種の健診やがん検診も行い、胃や大腸の内視鏡検査にも対応可能です。外来診療と一般病棟への入院、長期の療養入院、緩和ケアなど、患者さんのライフステージに合わせて当院を活用していただけるでしょう。また、当院がある瀬谷区の高齢化率は横浜市の平均を上回っていますから、高齢になっても地域の中で安心して長く暮らせる療養環境を整えることが重要と考えています。
外来診療や一般病棟ではどんな診療が中心なのですか?
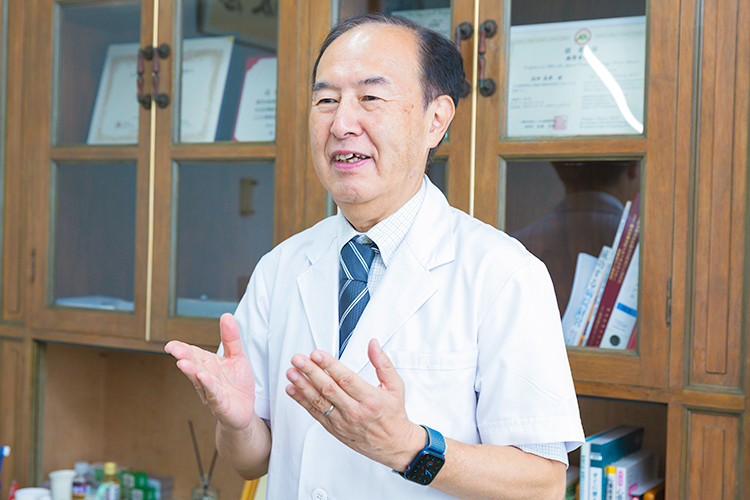
外来診療では、内科での一般的な内科症状の診療に加え、呼吸器内科の医師によるCOPD(慢性閉塞性肺疾患)やSAS(睡眠時無呼吸症候群)、循環器内科の医師による慢性心不全など、専門性を生かした診療を行います。横浜市の健診などで胃や大腸が再検査になった方は、当院で消化器内科の医師による内視鏡検査が受けられ、検査時に大腸ポリープの切除も可能です。皮膚科は多様な年代の皮膚トラブルのほか、アレルギー疾患などのお子さんの受診も多く、形成外科はアテロームなど皮膚の良性腫瘍の手術も行い、必要に応じて形成外科と協力して治療しています。耳鼻咽喉科では高齢の方の難聴、鼻炎などのアレルギー疾患まで幅広く対応し、重症な咽頭炎などは入院しての手術も可能。このほか一般病棟には急性期病院で治療を終えた患者さんへのリハビリテーションなど、ご自宅や施設にお戻りいただくために間をつなぐ役割もあります。
療養病棟や緩和ケア病棟はどのように利用されていますか?

療養病棟は、在宅療養中または特別養護老人ホームやグループホームなどに入所中だった高齢の患者さんが中心です。認知症、脳梗塞の後遺症、慢性心不全といった病気が悪化して、酸素吸入や喀痰吸引のような医療的措置が必要になり、ご自宅や施設での対応が難しくなって入院されるケースがほとんどで、入院期間も比較的長くなります。一方、緩和ケア病棟は、当院では末期がんの患者さんで50代くらいから80代くらいまでの入院が多く、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院のような病院や在宅療養から移ってこられます。当院では緩和医療に専門性を持つ医師が病棟を担当して医療用麻薬で痛みの緩和に努めるほか、非常勤で精神科の医師も在籍しており精神面のケアも対応可能です。さらに日本看護協会緩和ケア認定看護師をはじめ経験豊かな看護師がそろい、包括的に患者さんを診ていくなど緩和ケアの診療体制は非常に充実しています。
地域での医療や介護の連携について教えてください。

当院の地域連携室では、療養病棟、緩和ケア病棟および外来患者さんの一般病棟への入退院まで担当し、患者さんを紹介いただく病院の連携室、開業医の先生方と緊密に連携。院内では病棟でのカンファレンスに地域連携室のケースワーカーも加わり、退院後の支援体制も検討するなど、患者さんとご家族を包括してケアする体制です。地域で在宅医療を担う医療機関とも連携を深め、それぞれの医療機関が診ている在宅療養の患者さんの緊急入院にも対応。また当院で訪問診療を担当する高齢者施設には、週に1回、常勤の医師が看護師とともに訪問し、現場でクラウド型の電子カルテを参照しながら患者さんを診ています。その際も容体の悪化などで入院が必要と判断すれば、連絡を受けた当院はすぐに受け入れ準備に入ります。クリニックと急性期の大型病院、それぞれで診る患者さんの間にいて、受け入れ先が見つかりにくい患者さんを受け入れることが重要と考えています。
院長就任後の感想と今後の展望をお聞かせください。

2025年7月に院長に就任して感じたのは、職員全員がとてもやる気があって、患者さんの治療や対応に一生懸命に取り組んでいることです。診療時間ぎりぎりの入院の相談でも、当日に引き受けようと看護師長も含め各職種が頑張ってくれ、本当に「地域のために」という想いが強いのだと思います。一方、今後の展望では診療内容のさらなる充実を図る予定です。以前に行っていた下肢静脈瘤の治療を再開し、急性期治療後の患者さんを受け入れて体力や身体機能の改善を図るリハビリテーションに加え、外来でのリハビリテーションも検討中です。より長期的な展望では建物の建て替え計画も進行中ですが、病院全体としては複数の病気をお持ちの患者さんには内科と整形外科が連携して診療し、リハビリテーションも提供でき、在宅療養中でも病状が悪化したら再度入院できる。そんな地域に根差した病院づくりを進めながら、新たな環境への移行を考えていきたいと思います。
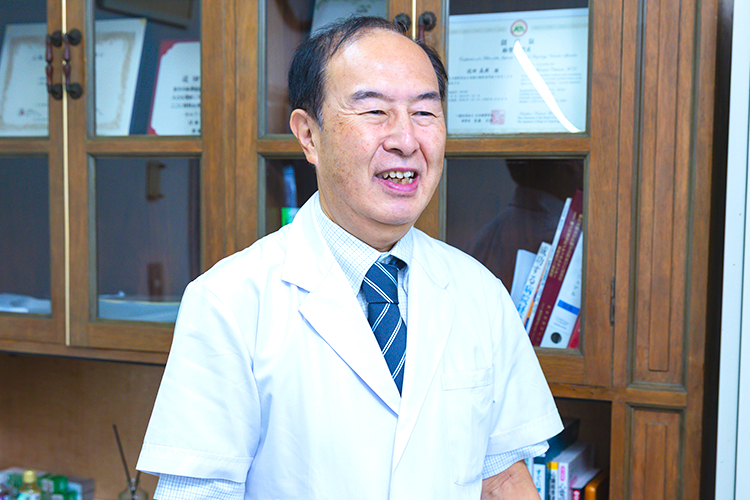
近田 正英 院長
1985年東京大学医学部卒業後、同大学医学部附属病院胸部外科に入局。東京共済病院外科、国保旭中央病院心臓外科を経て、1991年に東京大学胸部外科助手に就任。1996年からアメリカ国立衛生研究所に研究員として留学。帰国後は国立小児病院(現・国立成育医療研究センター)心臓外科、聖マリアンナ医科大学心臓血管外科講師、同大学心臓血管外科教授を歴任。小児および成人の先天性心疾患を専門とする。





