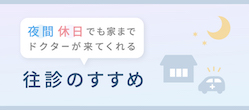一般社団法人巨樹の会 五反田リハビリテーション病院
(東京都 品川区)
松谷 雅生 院長
最終更新日:2020/11/25


手厚いケアにより地域の回復期医療を牽引
五反田駅から8分の地にある「五反田リハビリテーション病院」。脳卒中や骨折など、急速に生活機能が低下する疾患には、速やかな治療に加えて早期の適切なリハビリテーションが求められる。同時に、障害の重度化を防ぐには、急性期から回復期、そして地域で生活する段階に至るまで、それぞれの時期に適した継続的なリハビリテーションが必要だ。同院は、こうした各段階において、機能訓練や日常生活動作の向上を中心とした回復期のリハビリテーションを提供。240床というベッド数に対して、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士合わせて190人近くという多くの技士を擁している点が特徴といえる。スタッフ層の厚さを生かして行われるきめこまやかなケアに加え、屋上庭園や大浴場、和室を活用してのリアリティあふれるリハビリテーションメニューが充実。退院後の生活をスムーズに行うための配慮が随所にちりばめられている。患者への気配りに満ちた同院を率いる松谷雅生院長に、理念や特徴を聞いた。(取材日2016年6月8日)
貴院の長所をお聞かせください。

当院が所属する「巨樹の会」グループの在宅復帰率は、高い数値を保っています。担架で運ばれ、食事以外は寝たきり状態だった患者さんが、2週間後には「支えられていれば歩ける」段階まで回復する様子を初めて見た時は、私も驚いたものです。訓練の環境としては、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士合わせて約190名もの技士を擁し、1年365日、休みなくリハビリテーションに取り組める場を整備。慣れている患者さんは1日3時間ほど行います。訓練が進むとお腹が空きますから、その分食べれば筋肉の量も増えます。運動を重ね、栄養に配慮がなされた食事を取ることで血圧が下がり、血糖値が下がる例も多いですね。食事については、退院後、地域で暮らす際に不可欠となる「一人での食事」を目標に、109名の看護師と78名のケアワーカーが練習をサポート。回復に至るまでのプロセスの充実は、当院の大きな特徴といえるでしょう。
患者からのニーズはどのように感じておられますか?

当院を選んだ理由を聞いてみると「入院するなら都市部と決めていた」というお声が多いです。都会の生活を好んでいる患者さんにとって、五反田の駅から近いという要素は大きいのでしょう。ビルの見える街中で長く過ごしてきた方は、満天の星が広がる大自然よりも、自分の日常に近い感覚で過ごせる場所の方が良いこともあるのかもしれませんね。リハビリテーションの過程の一つに「外出」があるのですが、車が行き交う大通りを歩くうちに、自分の居場所に戻ってきたな、と感じる患者さんも多いのではないかと想像します。品川駅まで電車で行き、階段や人の波を経験して帰ってくるという訓練もあるんですよ。都市部にあるとお見舞いに来やすいですから、患者さんのご家族にも喜ばれますね。訓練は時にはハードですから、お見舞いの力に助けられている方はたくさんいらっしゃることでしょう。そういった点を踏まえても、アクセスの良い立地は長所の一つですね。
地域における貴院の役割をどのようにお考えでしょうか。

患者さんの中には「居住地は遠方だけれど、息子が近くに住んでいるから」と当院を選ばれる方もいらっしゃいます。しかしそれはほんの一部。多くの患者さんは、脳卒中や転倒などによってお住まいから比較的近くの急性期病院に搬送され、そこを経て当院へ入院されます。これまで当地域には、著名な病院は数あれど「回復期のリハビリテーションといえば」と呼ばれるような病院がありませんでした。そんな中で開院した当院の役目は、急性期病院内だけで抱えていた患者さんの受け皿になること。我々が患者さんを受け入れることで急性期病院のベッド数の空きが増えれば、より多く入院が実現するでしょう。当院が地域医療のお役に立てているのであれば、こんなにうれしいことはありません。回復期リハビリテーション病院だからこそできる地域貢献をめざし、今後も医療の充実をめざしていきます。
患者さんの受け入れに関して気をつけていることは何ですか?

可能な限り、判断する過程を円滑に進めるようにしています。入院を希望する連絡はファックスで届くことが多いのですが、遅くとも打診された翌朝までには、医療連携室の看護師、副院長、そして私で集まって会議を実施。入院の準備を素早く行います。もし費用的な面で「個室は厳しい」という要望があれば、「今すぐだと個室しか案内できないが、いつ頃には4人室に移れるので個室と4人室を組み合わせての入院はどうか」といった具体的な提案をするケースもあります。急性期の入院と違って数ヵ月間にわたり滞在される方もいらっしゃるわけですから、その辺りは配慮してお返事しますね。訓練においても、退院の約1ヵ月前にソーシャルワーカーが患者さんのご自宅に訪問し、ご自宅の中や周辺の段差などの状態を確認。その動きに特化した訓練を行います。合わせて「このぐらいの踏み台があるといいでしょう」など、退院後の生活がスムーズになるような助言にも心を
充実のリハビリテーションを実現できる理由をどうお考えですか。

われわれが所属する「巨樹の会」グループは、「できる限り患者さんを受け入れる」という目標のもとで発展してきました。もともとは総合病院として医療の提供を行ってきた当グループが回復期医療に関わるようになったのは、急性期の次の段階に患者さんをお送りする必要が出てきたため。合わせて、看護やリハビリテーションをはじめとした「患者さんに接する人材を鍛え、増やすこと」の重要性に気づき、看護やリハビリテーションの専門学校を設立。患者さんをいかに受け入れるかを念頭に置きながら、時代に応じた進化を遂げてきたからこそ、当院のようなリハビリテーション内容と人材の配備が可能になっているのだと考えます。グループの理念やこれまで積み重ねた実績を守りながら、今後も進化を続けていかなくてはならないと思いますね。

松谷 雅生 院長
1968年東京大学医学部卒業。東京大学医学部助教授、埼玉医科大学教授などを経て2015年より現職。脳神経外科を専門とし、急性期の医療に従事した経験を生かし、日々の業務にあたる。耳鼻科の開業医だった父の影響から医学の道へ。休日の楽しみは野球観戦と観劇。それぞれの魅力を「一言で説明するのは難しいのですが、合理的な説明ができないからこそ惹かれるのだと思います」と語る。